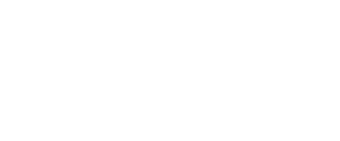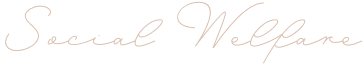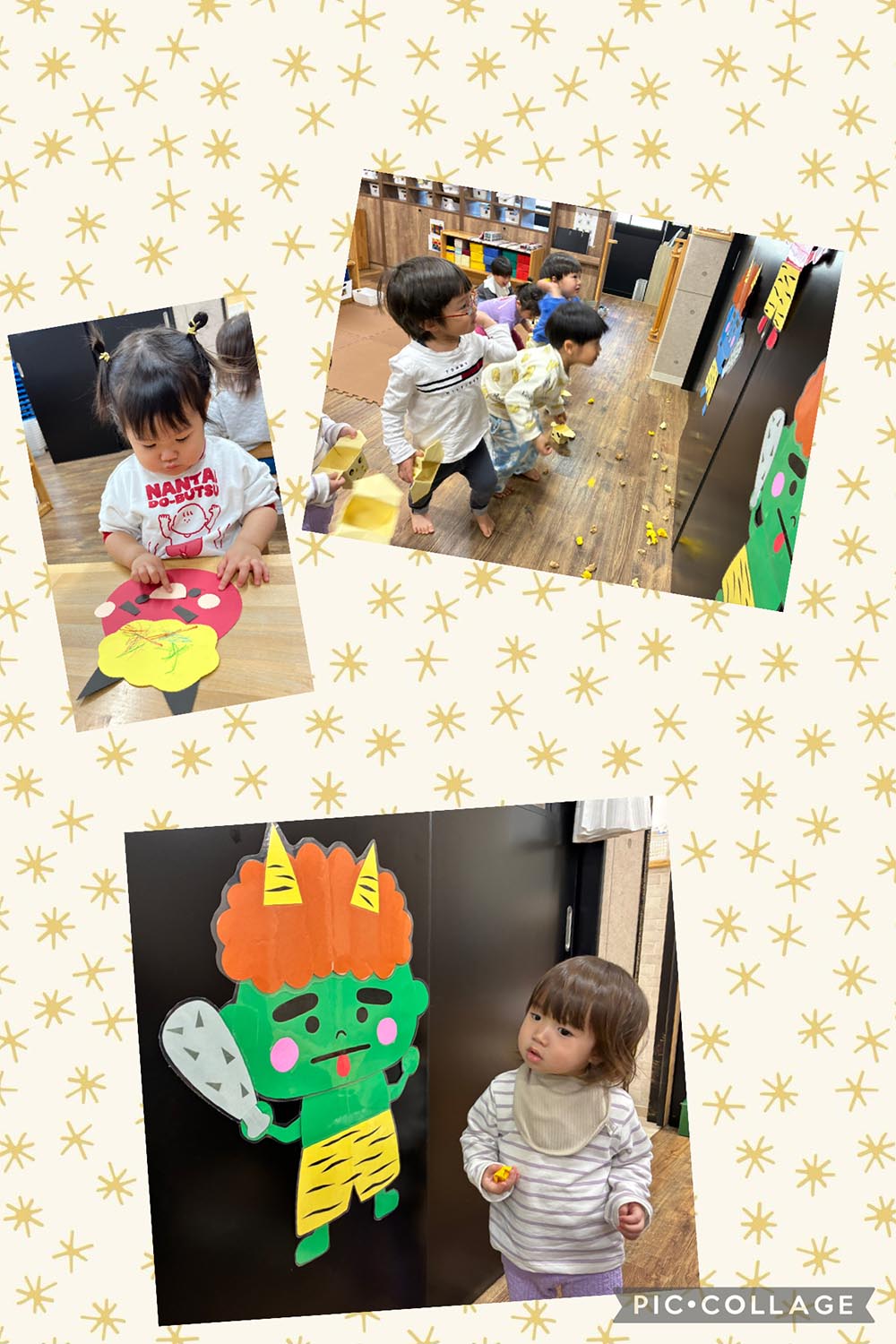体力勝負の仕事だからこそ

保育や調理といった職種は、一見華やかで子どもたちや園児たちの笑顔にあふれた仕事ですが、実際には体力と気力の両方を使う「体力勝負」の仕事でもあります。毎日、立ちっぱなし、動きっぱなし、気を張りっぱなし――そんな日々が続くなかで、心も体もすり減らしてしまう人が後を絶ちません。
そのような現場だからこそ大切にしたいのが、「休み方」です。適切に休むことは、質の良い仕事を続けていくために欠かせないセルフケアの一つです。
このコラムでは、保育士・保育補助・調理スタッフといった園で働く方々に向けて、なぜ「休み方」が重要なのか、どうすればうまく休めるのか、そして職場としてどのような工夫が求められるのかを具体的にお伝えします。
1. 保育・調理の現場はなぜ「体力勝負」なのか
保育や調理の仕事には、共通している特徴があります。それは、目まぐるしく変化する日々の業務を、身体を使ってこなすという点です。
保育の現場
保育士は、子どもたちの成長を支える大切な存在です。抱っこ、追いかけっこ、散歩の引率、トイレの補助、食事の介助、掃除や洗濯…。一つひとつは日常的な作業であっても、積み重なると非常に体力を消耗します。特に未満児クラスでは、体力的な負荷が大きくなりがちです。
調理の現場
調理スタッフもまた、朝から昼にかけてノンストップで働くことが多く、立ち仕事が中心になります。大量の調理、衛生管理、アレルギー対応、配膳、後片付けまで、時間との勝負のなかで集中力と体力を保ち続けなければなりません。
2. 「疲れをため込まない」ことの大切さ
体力的・精神的に負担が大きいからこそ、疲労を感じたときにしっかりと休むことが重要です。疲れをため込むと、集中力が低下し、思わぬ事故やミスを招くリスクが高まります。
慢性的な疲労がもたらす影響
- ケガや事故の増加(転倒、ぶつかり事故など)
- 保育中の注意不足によるヒヤリ・ハットの発生
- 子どもへの対応の質が低下
- 周囲への配慮が欠け、人間関係の悪化に繋がる
- 感情のコントロールが難しくなり、イライラや怒りが表面化
こうした負の連鎖を防ぐには、適切な「休み方」を身につけておく必要があります。
3. 休み方には「技術」がある
単に休憩時間を取れば良いというものではありません。質の高い休息には「技術」と工夫が必要です。
こまめな「小休止」でリズムを整える
- 朝の活動後、昼食前、午後の活動の合間など、意識的に「小さなリセットタイム」を入れる
- 深呼吸を数回行うだけでも、自律神経が整い、集中力が回復する
- ストレッチや軽い体操も効果的
睡眠の質を高める
- シフトの関係で生活リズムが乱れがちな方は、睡眠時間より「眠りの深さ」に注目
- 寝る前のスマホ使用を控え、ぬるめのお風呂に浸かる、アロマなどのリラクゼーションを取り入れる
- 休日の寝だめよりも、毎日の安定した入眠習慣を優先することが重要
心を休ませる「メンタルの休息」も大切に
- 休日に詰め込みすぎない
- 他人のための時間(家事、育児など)を「自分の時間」と分けて捉える
- 趣味や好きなことに没頭する時間をつくる(絵本を読む、音楽を聴く、散歩をするなど)
4. 「休みにくい」職場環境があることも事実
現場の人手不足や、周囲への遠慮の気持ちから「休めない」「休みにくい」と感じている方も少なくありません。
よくある声
- 「休むと同僚に迷惑をかけてしまう」
- 「体調不良を伝えたら冷たい目で見られそう」
- 「有給が取りづらい雰囲気がある」
こうした空気は、長期的には組織にとってもマイナスになります。休息を取らずに限界を迎えることで、離職につながる可能性もあるためです。
5. 組織ができる「休みやすい仕組みづくり」
職員一人ひとりが気持ちよく休める環境を整えることは、園全体のパフォーマンスを高めることにもつながります。
休みやすい文化をつくるために
- 管理者が率先して休みを取得する姿勢を見せる
- 定期的なシフト調整やヘルプ体制の整備
- 有給取得目標や分散取得の仕組み化
- 急な体調不良でも対応できるバックアップ要員の配置
「休むことが迷惑ではなく、当たり前のこと」と捉えられる組織づくりが、結果的に働く人を長く支えることになります。
6. 「働き続ける力」は、休み方で決まる
保育・調理の仕事は、誰かの生活を支える尊い仕事です。その使命感ゆえに無理をしてしまう人も多く見られます。しかし、長く、無理なく働き続けるには、無理をしない「勇気」や「仕組み」が必要です。
大切なのは、自分の体調と心の状態に耳を傾け、こまめにリセットすること。自分自身を大切にすることが、子どもたちや仲間を大切にする力にもつながります。
最後に:休むことは、働くことの一部
「休むことは、怠けることではない」と伝えることが求められています。むしろ、良い仕事をするために、そして安心安全な保育・調理を提供するためには、積極的に休みを取ることが必要です。
体力勝負の現場だからこそ、今こそ「正しい休み方」に目を向け、心と体に優しい働き方を模索していくことが求められています。